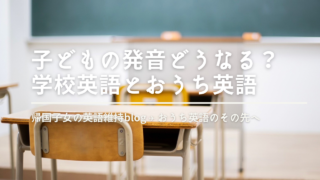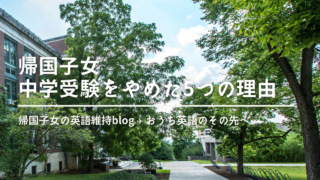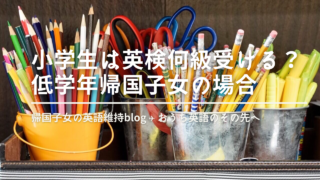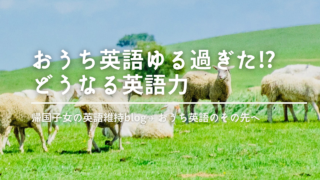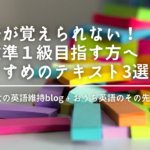わたしは長い間子供たちの進路について、悩み続けてきました。しかし私の心配をよそに、結局子供たちは自分で進路を選び、自分に合った高校・大学を自分の力で選び抜いていきました。
この記事では、長女(高2)がどのような進路をどのような理由で、どのタイミングで選んだか、ご紹介しようと思います。
帰国子女が100人いたら、100通りの海外生活があり、100通りの進路、そして100通りの考え方があります。そのうちの1人の進路です。「そんな考え方や進路があるだな」と参考にしていただければ幸いです。
【帰国子女】中2秋に帰国した長女
長女は幼少期をアメリカ現地校、その後中国の日本人学校で過ごし、中2の秋に帰国。地方の公立中へ転入しました。
地方田舎の町には、帰国子女が行くようなインターや国際校はありません。私たちは一時帰国の度に、地元の私立・国立中高一貫校を見学していました。また、公立中の体験入学もしました。その上で、娘が選んだのは「公立中へ転入して高校受験をする」というものでした。
親としては、せっかく地元私立有名校に編入出来るチャンスだったのに…と非常に残念に思い、何度も娘を説得しましたが、娘の気持ちは固まっていました。
一時帰国の学校見学体験談はこちら
【高校受験を選んだ理由①】すでに行きたい大学が定まっていた
中学生にして娘は「日本のこの大学のこの学部でこの勉強がしたい」と決まっていました。そして、目指す大学の附属高校を迷わず受験しました。この強い希望進路は、中国の日本人学校で経験した、ある体験があったからです。
我が子が通っていた日本人学校では、毎年中学生を対象に進路講演会がありました。その時の、ある方の講演が大きく影響していたのです。娘は多感な思春期に、海外で活躍する方の講演を度々聞ける機会があったので、とても恵まれていたと思います。
自分の将来について初めてじっくりと考えたのが海外。しかも日本人学校。同じ日本人でありながら、さまざまなバックグラウンドの生徒が集まる日本人学校で、娘は自分の生いたちをどのように考えたのでしょう。親の私にも想像できないことでした。
【高校受験を選んだ理由②】海外の大学へ進学する気はなかった
多くの方がびっくりするのですが、娘は海外の大学へ進学する気はありませんでした。たいていの人は「帰国子女なら海外大学に行く」と思いますよね。親のわたしですらそう予測してました。ところが娘ははっきりと「日本の大学へ進学する」と中学生の時に決めていました。
現在娘が通っている高校では、海外有名大学の講義を受けたり海外大学へ研修へ行ったりして海外大学を身近に体験させてもらえます。それでも海外の大学へ行きたいとは言いません。「1年や半年の留学はしたいかもしれないけど、海外大学にどっぷり4年間は考えられない」と言っています。
その理由はアメリカで体験した人種差別、アジア人差別が大きく影響しています。
娘は6〜10才をアメリカ現地校で過ごしました。遊んでいるだけで友達になれる時期を終え、人間関係が深まり始める年齢です。娘はこの頃、米国現地校でアジア人差別を経験していたのです。
それは、親の私からみてもあからさまなアジア人差別でした。いえ、差別は言い過ぎですね。人種のヒエラルキー。これをはっきりと見せつけられていました。
私たちが住んだのはアメリカ中央部の田舎町。白人主義の州でした。学校の先生は100%白人。生徒は白人が7割、残り3割がアジア人、スペイン系など。多国籍とはいえ、圧倒的白人の多い地域でした。
白人の子たちは、とても目立ちます。華やかです。自信をもっています。手足が長くしなやかで、美しい絹のようなブロンドの髪、夏空のような瞳。アジア人には敵わないものを生まれた時から持ち合わせています。
娘がGrade3の時。その子たちは集まり「CLUB」を作り、娘は仲間に入れてもらえない、ということがありました。日本の女の子でもありますよね。目立つ女の子たちが集まり、どこへいくのも一緒に行動するような集団。娘は、その白人のうちの1人と仲良くしたかったのですが「CLUBだから無理」と言われいつも仲間外れにされていました。
それがあからさまなのです。白人以外の子は絶対にCLUBに入れてもらえません。それは学年が終わるまでずっと続きました。
その後娘は、親しくなった(ちょっと浮いた)白人の女の子がいたのですが、友達というより下僕のような扱いを受けていました。仲良くなりたいのに、人種のヒエラルキーが小学生からあるのか…とショックでした。
また、近くの高校のパレードを見に行った時。白人男女の生徒は先頭の華やかで派手な演出。全身で青春していました。しかし、その他の人種の子たちが先頭チームに見ることはありませんでした。
この体験は娘だけでなく、私自身も経験しました。現地でのアジア人を見下す態度、無視。あるお店では黒人スタッフから嫌がらせを受けたこともあります。「ここにずっとは住めない」と痛感しました。アジア人差別は、家から出たらいつもすぐそこにあったのですから。
娘は、幼い心に人種のヒエラルキーを感じ、いくら自分が頑張っても白人には勝てないアジア人であることを、身をもって知っていたのです。
だから勉強のためだけに1年や半年間の留学はアリだけど、大学生活全てをアメリカで過ごすことはできない、と判断したのでしょう。
また中国では、反日思想がいまだ強く、中国在住中に身の危険を感じることもありました。中国人による反日運動が強かった頃、私たちは米国でした。領事館から日本レストランへ行くことを禁止する警告メールがあったり、日本車に乗っている日本人は外出を控えるなど、日本人はアメリカにいても脅かされていました。
帰国子女は海外大学に進学する、と多くの人が考えているかもしれません。しかし我が家の場合は、海外に住んだからこそ知ってしまった現実に、これ以上立ち向かうことは出来ませんでした。
【高校受験を選んだ理由③】自分のアイデンティティが迷子だった
娘は5歳まで日本で過ごしたのち、アメリカへ引っ越ししました。残念なことに日本の思い出は全く覚えてないとのこと。1番古い記憶がアメリカです。そのため、自分が育った街はアメリカと中国なのです。記憶の中の自分は英語を話し、外国人と遊び過ごした思い出ばかり。
また中国では日本人学校へ行きましたが、半数が国際家庭(ハーフのお子さん)、半数は何カ国も駐在してきたような子や生まれた時から中国に住んでいる日本人など。共通しているのは「日本語が話せる」ということだけで、日本人学校全員のバックグラウンドがみんな違うクラスメイト。どれほど豊かな思考をもち、お互いの経験を認め合う仲間だったことでしょう。
そんな仲間と中2まで過ごし、転校した先の日本の地方公立中。クラスの大半が飛行機にのったことがなく、でもなぜかみんなこの地元は全国的ににみても都会だと思っている思考にびっくりしたと言っていました。
そこで「違う」と言えなかった娘。
周りの空気に合わせ、自分が見てきたこと体験してきたことを話せる状況でもありませんでした。周りの空気に合わせ続け、孤独な日々だったと思います。
帰国してから、娘は自分のアイデンティティが完全に迷子になっていました。
生い立ちが自分だけ違うという状況がどれほど娘を生きにくくしていたか。
誰とも今の気持ちを共感できない、共感してもらえない、言えない、共有できない。息苦しかったと思います。
さらに、県外受験で帰国生のたくさんいる大学附属校を第一希望とすること。そんな娘を応援してくれる人は、誰1人いませんでした。
中学校の進路担当や担任の先生からは何度も「地元高校に進学して地元に馴染むこと」を強要されましたが、娘の気持ちは変わりませんでした。
親の私が出来ることは、いつも娘の1番の味方でいること、そして娘が自分で選んだ高校と大学の進路を、精一杯応援することでした。
【帰国子女の選んだ進路】国内首都圏の高校・大学へ進学
娘は無事に第一希望の高校に合格し、希望する日本の大学への進学が確定しました。今 娘は、様々なバックグラウンドをもった生徒が集まる学校で、お互いを認めあい、共感し合える友達と出会え、水を得た魚のように高校生活を送っています。
15歳で親元を離れ寮生活を送ることは、親はとても寂しいです。しかし、娘は自分のアイデンティティを確立し、心を成長させている大切な時間。これは地元にいては出来ないことです。
また、娘は高校へ進学してからこのような言葉を発しました。
「国際人とは、差別を受けても生きていく力を持っている人」
これは、経験しないと言えない言葉です。経験から出た言葉です。私は幼い娘が海外でどれほどの想いをしながら生きていたんだろう、と胸が痛むほどでした。
海外生活は、住む国によって全く感想が違います。インド、シンガポール、マレーシア、インドネシアなどの東南アジアは親日国。同じ帰国生でも海外大学の捉え方は娘と全く違うことでしょう。
そこも含めて、娘は自分の進路を改めて考え、今後も自分で進路を決めていくことでしょう。
海外駐在は親の都合で子供の転校を繰り返させてしまいました。だから、流される性格になっていないかなと案じていましたが、娘は経験を通して、自分で選び決める力をつけていたのです。
以上が、帰国子女の娘が決めた進路のお話でした。ナイーブな内容のため、うまくまとまっておらず、乱筆で大変申し訳ありません。思い出したエピソードなどがあれば、また加筆していきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。こんな帰国子女の考え方もあるんだな、と参考にしていただければ幸いです。